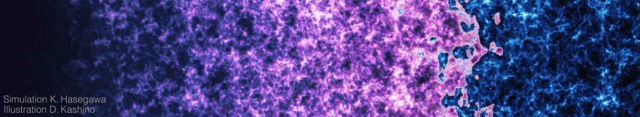Seminars in April
Speaker
Shinsuke Asaba
Date/Place
13:30-, 12(Thu), Apr. @ES606
Title
Evolution of the
density fluctuations and imprints on CMB
Abstract
宇宙は、宇宙論のスケールでは限りなく一様で等方的であると考えられている。しかし、宇宙の大規模構造を説明するためには、宇宙初期において、揺らぎが必要である。1965年に、マイクロ波が天球上の全方向から等方的にやってくるのが観測された。このマイクロ波のスペクトルは絶対温度2.725Kの黒体輻射とよく一致していた。このマイクロ波は宇宙マイクロ波背景放射(CMB)と呼ばれ、宇宙が限りなく一様で等方的である証明となっている。また、このマイクロ波のスペクトルは宇宙の晴れ上がりのときの情報を持っており、解析すると揺らぎがあることが分かっている。
本研究では、まず、膨張宇宙における宇宙の晴れ上がりまでの揺らぎの進化について、数値的に計算し、宇宙の構成要素(光子-バリオンプラズマ、ダークマター、ニュートリノ)ごとにどのようにふるまうかを調べた。次に、宇宙の晴れ上がりのときの揺らぎから、CMBのスペクトルを計算し考察を行った。
Speaker
Chiho Kubota
Date/Place
13:30-, 12(Thu), Apr. @ES606
Title
Gravitational
lensing and cosmology
Abstract
重力レンズ効果は、一般相対性理論にてその現象を示唆され、実際に1919年の皆既日食の際には一般相対性理論の証明にも繋がった。重力レンズ効果の特徴として、①像が複数見える(実在の天体は見えない)②像が変形される(実際の天体の形とは異なる)③増光されるがある。
今回の研究では、まず重力レンズ効果がどのようにして起きるかを理解するために、3つの現象の公式を数学的に計算していくことで求めた。補足的な意味で、重力レンズがどのように宇宙論に使われるかも簡単に調べた。
Speaker
Shouhei Saga
Date/Place
13:30-, 12(Thu), Apr. @ES606
Title
Generation of
primordial magnetic fields and their observational constraints
Abstract
現在宇宙のいたるところで磁場が観測されているが、その起源はよくわかっていない。候補の一つとして、インフレーション中に磁場が生成されたと考
えられている。しかし、通常の電磁気学ではConformal invarianceであるので真空が保存され、量子ゆらぎで磁場が生成されない。
卒業研究では、Conformal invarianceを破る作用をレビューし、そこに現れるパラメーターの制限を行った。その中でback reactionの問題、Strong
couplingの問題があり、無矛盾な磁場生成が困難であることが分かった。
Speaker
Yuki Shibusawa
Date/Place
13:30-, 12(Thu), Apr. @ES606
Title
Gravitational
nonlinear evolutions in the baryon, hot dark matter and warm dark matter models
Abstract
近年、宇宙の大規模構造や宇宙の背景放射の温度ゆらぎなどから、宇宙の成分などの宇宙論パラメータを極めて正確に見積もることが可能になってい
る。これを可能とした主要な原理として、宇宙の密度ゆらぎの進化が用いられる。ゆらぎの小さい領域ではゆらぎの成長は線形理論で記述できるのに対し、線形近似が成り立たない非線形領域ではゆらぎの成長を解析に取り扱うことは
困難である。このような非線形領域でのゆらぎの進化を追うためには、数値シミュレーションが有効である。
本研究ではまずゆらぎの線形理論を学び、次に数値シミュレーションを用いてbaryon、hot dark matter、warm dark matter
modelにおける構造形成について考察を行った。
Speaker
Naoshi Sugiyama
Date/Place
13:30-, 19(Thu), Apr. @ES606
Title
Policy speech
Abstract
Policy speech
Speaker
Takahiko Matsubara
Date/Place
13:30-, 26(Thu), Apr. @ES606
Title
Syntheticism on the
primordial non-Gaussianity and scale-dependent bias
Abstract
大規模構造におけるスケール依存バイアスは、初期非ガウス性を制限する有力な方法である。これを解析的に導出する方法はいくつか知られているが、非線形領域のバイアスが絡むため、近似によって異なる結果が得られている。それらの中ではピーク背景分離法による予言がシミュレーションともよく一致することが知られている。
今回、非局所バイアスを取り扱える統合摂動論の枠内で、ピーク背景分離法を使わずにスケール依存バイアスを導いた。得られた結果は、ある種の極限でピーク背景分離法の表式を完全に再現する。すなわち、より一般的な解析予言が得られたことになる。
Seminars in May
Speaker
Kiyotomo Ichiki
Date/Place
15:00-, 10(Thu), May. @ES606
Title
Effects of CO line
emission on CMB power spectrum and its analysis
Abstract
近年の宇宙マイクロ波背景輻射(CMB)温度揺らぎの精密な観測により、宇宙の構成要素や宇宙年齢などが驚くべき精度で決定されつつある。しかしながら、現在観測データ取得中のPLANCK衛星では、高感度、高分解能を誇る検出器(High
Frequency Instruments;
HFI)の観測帯域に、前景成分として非常に強度の強い一酸化炭素分子輝線が含まれているため、これまでとは違った新しい前景放射の差し引き手続きが必要となる。
これを受けて、我々は「なんてん」望遠鏡による比較的高銀緯にある分子雲領域の輝線データを用いて、PLANCK検出器によるシミュレーション観測を行った。今回解析を行った領域では、一酸化炭素分子輝線による温度揺らぎの角度パワースペクトルは、小角度スケールほど大きな振幅をもち、10分スケールで予想される宇宙論的温度揺らぎの30%に達していた。この一酸化炭素分子輝線によるCMB角度パワースペクトルと、その揺らぎが宇宙論パラメタ推定へ与える影響について紹介する。
また、独立成分分析の手法の一つであるFastICA法を応用し、CO成分の除去がどの程度可能か検討した。FastICA法の簡単な紹介と、そのCO成分の除去によりどの程度パワースペクトルが復元されるかを示す。
Speaker
Kenji Kadota
Date/Place
13:30-, 17(Thu), May. @ES606
Title
The effect of quark interactions on dark matter kinetic
decoupling and the mass of the smallest dark halos
Abstract
Speaker
Chiaki Hikage
Date/Place
13:30-, 24(Thu), May. @ES606
Title
Reconstruction of
BAO Ring
Abstract
バリオン音響振動(BAO)は、宇宙膨張の様子を探る上で大変重要な観測指標である。構造進化の非線形性によって、BAOのシグナルは弱まるが、Eisensteinらによって開発されたReconstruct法を使うことで、BAOスケールの決定精度が大きく向上することが確かめられた
(Padmanabhan et al. 2012)。今回、Reconstruction法を概説するとともに、ReconstructionしたBAO
Ringの非等方性から、H(z), DA(z)を独立に制限した結果を紹介する。
Speaker
Toyokazu Sekiguchi
Date/Place
13:30-, 31(Thu), May. @ES606
Title
CMB optimal constraints on Non-Gaussian isocurvature
perturbations
Abstract
Non-Gaussian isocurvature perturbation is a unique
probe for the physics of the very early Universe. As isocurvature perturbation little
affects the structure formation at late times, it can be best constrained from
observations of the cosmic microwave background (CMB).
I will show how we can obtain optimal CMB constraints on the isocurvature
non-Gaussianity and present a current one from WMAP data.
Seminars in June
Speaker
Maresuke Shiraishi
Date/Place
13:30-, 7(Thu), Jun. @ES606
Title
Statistical
anisotropy in the CMB bispectrum
Abstract
Primordial non-Gaussianities are key features to
judge the validity of the inflationary models; hence they has been constrained from the
CMB bispectra. In these studies, the symmetry under the rotational transformation have
been assumed despite a fact that there also exist theories involving the violation of
the rotational invariance at the non-Gaussian level. In our recent work, we have newly
computed the CMB bispectra induced by the symmetry-breaking non-Gaussianities and found
some characteristic signals.
In this seminar, I would like to present a set of results.
Speaker
Shogo Masaki
Date/Place
13:30-, 14(Thu), Jun. @ES606
Abstract
銀河進化を明らかにするうえで、種々の観測結果を再現し、解釈付けを行うことが必要である。そのためには、銀河とダークマターハローを結びつけることは重要な要素となる。これまでに数々の試みが行われており、Halo
Occupation Distribution(HOD)モデルやSubhalo Abundance
Matchig(SHAM)モデルが開発されている。HODは、計算が簡易であるが、多数のフィッティングパラメータを要するといった問題を含んでいる。一方で、SHAMは計算コストが高いものの、non-parametricモデルであり、現在注目されているモデルである。
本研究ではSHAMに着目する。まず、SHAMの問題点を議論し、それを踏まえてモデルを拡張し、SDSSで得られた銀河の二点相関関数や銀河周りの密度分布との比較を行う。
Speaker
Masanori Sato
Date/Place
13:30-, 21(Thu), Jun. @ES606
Title
Cosmological
parameter estimation with convergence bispectrum of weak gravitational lensing
Abstract
宇宙マイクロ波背景放射の観測から、宇宙初期の密度揺らぎは、ほぼガウシアン統計に従うことが知られているため、宇宙初期の宇宙論的な情報はパワースペクトルを調べることで尽きていると考えられる。しかし、現在観測されている大規模構造などは非線形重力進化の影響から、非ガウス統計に従い、高次の相関も持つことになる。従って、パワースペクトルだけでなく、バイスペクトルに含まれている宇宙論的情報が、どれほど宇宙論パラメータの推定へ影響を及ぼすかを調べることは重要である。
我々は、重力レンズのconvergence場に注目し、Seo et al. 2012 (ApJ, 748, 57)で行われた重力レンズシミュレーションを用いた。1000
realizationのシミュレーションからパワースペクトル、バイスペクトルの共分散行列を求め、宇宙論パラメタの制限をフィッシャー解析を用いて行った。バイスペクトルが宇宙論パラメータの制限をどれほど改善するかを示す。また、パワースペクトルとバイスペクトルのクロス共分散がパラメータ推定に与える影響についても話す。
Speaker
Hayato Shimabukuro
Date/Place
10:00-, 28(Thu), Jun. @ES606
Title
21cm absorption by
minihalos
Abstract
ビッグバンから約38万年後、それまで電離ガス状態であった宇宙の物質は中性化し、それからしばらく光を放つ天体の存在しない、いわゆる暗黒時代が続いた。その後、密度揺らぎが成長し、初期の天体が形成された。暗黒時代の観測は現在の技術では困難だが、今後、発展が期待される電波観測で可能になると考えられている。そこで本研究では、暗黒時代に存在するミニハローと呼ばれる初期天体中の、H1ガスの21cm線電波による吸収に注目する。ミニハローとは、暗黒物質と水素ガスが重力収縮したものの、ビリアル温度が低いため、効率的に冷却せず銀河になることができなかった、初期銀河に比べて軽い天体である。また、21cm線電波とは、中性水素の超微細構造由来の波長21cmの電磁波である。
今回のセミナーでは、研究の進捗報告を行う。具体的には、これまで行ったミニハローの光学的厚さと存在個数の関係を示す計算結果を示す。また、ミニハローの様な小スケールサイズの天体に影響を及ぼす物理として、ニュートリノ質量や、インフレーションによって生成される初期のパワースペクトルのrunningが考えられる。そこで、これらがミニハローの存在個数に与える影響を計算した。その結果、ニュートリノ質量よりもrunningの方がミニハローの存在個数に影響を与え、さらに高赤方偏移であるほどその影響が大きいということが得られた。以上の報告を今後の計画と併せて紹介する。
Speaker
Asuka Kataoka
Date/Place
15:00-, 28(Thu), Jun. @ES606
Title
Analysis of halo
clustering by anisotropic correlation function
Abstract
宇宙論パラメータに制限を与える距離指標として、バリオン音響振動(BAO)が注目されている。これまで、BAOによる宇宙論パラメータの制限には角度平均した2点相関関数が用いられてきた。だが、SDSSといった実際の赤方偏移サーベイでは、構造のスケールは非等方に変形する。その為、視線方向とそれに垂直な方向に分けて計算した2点相関関数(非等方相関関数)を用いる事で、宇宙論パラメータにより強い制限を与える事ができる。
本研究では、N体シミュレーションを用いて、赤方偏移変形を考慮した2点相関関数、非等方相関関数を計算した。また、線形理論による理論モデルとの比較を行った。
Seminars in July
Speaker
Yasushi Matsuda
Date/Place
13:30-, 5(Thu), Jul. @ES606
Title
Use of Cluster
Method ~reducing cosmic variance~
Abstract
前回は cluster methodを用いて cosmic variance
を減らすことを大まかに説明した。cluster
methodとは、クラスターでトムソン散乱し、偏光して我々にやってきたCMB光子を、多くのクラスターについて観測することで、多くのLSSを見ることができるという方法です。今回は、cluster
methodを具体的に数値計算し、どのようにcosmic varianceが減るのかを解説する。
Speaker
Akemi Kobayashi
Date/Place
15:00-, 5(Thu), Jul. @ES606
Title
Estimation of
gravitational waves from PBH mergers by using merger trees
Abstract
原始ブラックホール(PBH)は、宇宙初期に過密度領域が重力崩壊することにより生成されたと考えられる軽いブラックホールである。PBHは、宇宙の歴史の中で合体を繰り返し成長し、その過程で重力波を放出する。この重力波を見積ることが今研究の最終目標である。
PBHの合体過程を詳しく見ていくと、まず、生成されたPBHの周りには、ダークマターが降着しダークマターハローを形成すると考えられる。それらのハローが合体すると、その中でPBHも連星となり、合体していくと考えられる。そのため、PBH連星が、いつどのハローに属しているかを知ることが重要であるため、ハローのmerger
treeを考える必要がある。
今回のセミナーでは、merger treeについてと、連星合体の際に考えるべき物理過程について発表する。
Speaker
Takahiro Inagaki
Date/Place
13:30-, 12(Thu), Jul. @ES606
Title
The formation of
the Brightest Cluster Galaxies
Abstract
The Brightest Cluster Galaxy(BCG)
の形成過程について発表する。BCGとは銀河団の中心部付近に位置し、銀河団に付随する銀河の中で最も明るい銀河種族である。従って、BCGは様々な銀河の中で、星質量(規模)が最も大きい銀河種族であり、また銀河団の中心という特別な場所に位置している、という点において「特異である」である。BCGがさらに特異であることは、銀河質量-半径の関係が通常の銀河種族と異なる点である。このことはBCGが通常とは異なった形成過程であることを示唆している。
本セミナーでは、星を含めた宇宙論的N体シミュレーションを用いて解析した結果を発表する。
Seminars in August
Seminars in September
Speaker
Kohei Kumazaki
Date/Place
13:30-, 6(Thu), Sep. @ES606
Title
Probing galactic
magnetic fields by Faraday tomography
Abstract
現在、地球から銀河・銀河団に至る様々なスケールの天体がそれぞれ固有の磁場を持っていることが知られている。しかし、宇宙全体を満たす磁場の存在についてはまだ存在の有無も含めて理解されておらず、上限値が与えらている過ぎない。宇宙磁場は宇宙の大規模構造形成の過程にも大きな影響を及ぼすだけでなく、様々な天体現象を理解する上で非常に重要な役割を担っていると考えられる。そのため、宇宙磁場の理解は近代宇宙論の最重要命題のひとつにもあげられている。
この宇宙磁場に対して、将来の大規模電波望遠鏡の広波長帯偏波観測による解明が期待されている。広波長帯の偏波情報からその光子の経路上の磁場情報を階層的に得る方法としてFaraday
tomographyがよく知られており、銀河磁場のRotation measureの測定にも用いられている。本発表では、Faraday
tomographyを銀河間磁場探査に応用し、将来の広波長帯偏波観測でどれだけの結果が期待されるかを議論する。
Seminars in October
Speaker
Yoshitaka Takeuchi
Date/Place
13:30-, 4(Thu), Oct. @ES606
Abstract
21cm線は中性水素原始のエネルギー準位間の遷移にともなうスペクトル線であり、宇宙に満ちあふれている水素原子はその光源となり得る。そのため、21cm線の観測は星や銀河といった天体によって輝く以前の暗黒時代と呼ばれる時期を観測する唯一の手段ともされている。この21cm線もまた、我々に届くまでの間に大規模構造のつくるポテンシャルの中を通ってくることで重力レンズ効果を引き起こすが、21cm線の重力レンズ効果はCMBの偏光や銀河のシアーといったような特徴的な痕跡を残さないために観測は極めて困難とされている。
本研究では重力レンズ効果によって作られるtopologyの変化に注目し、ミンコフスキー汎関数を用いた解析を行い検出の可能性について議論する。
Speaker
Shohei Aoyama
Date/Place
13:30-, 11(Thu), Oct. @ES606
Title
Cosmological
phenomenology of decaying dark matter
Abstract
WMAP衛星による宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の温度ゆらぎの精密観測から、電磁相互作用や強い相互作用をしない冷たい暗黒物質(CDM)が宇宙全体のエネルギーの23%程度を占めていることが明らかになった。CDMは、その大部分は、未知の素粒子で構成されている可能性が高いと考えられている。しかし、暗黒物質粒子は直接観測には成功しておらず、その性質にも未知の部分が多い。
本研究では暗黒物質の持ちうる性質の1つである崩壊現象に注目した。特に暗黒物質粒子が複数の有限の質量の粒子に崩壊する場合は崩壊の寿命と娘粒子の質量に依存する構造形成になると予想される。本研究では暗黒物質(親粒子)が2つの有限の質量を持つ他の粒子(娘粒子)に崩壊する暗黒物質模型を考えた。まず、この崩壊を記述するボルツマン方程式を解いて、先行研究で求めた0次の運動量分布関数に対して摂動方程式を解いた。次に親粒子、娘粒子が膨張する宇宙の中でどのような密度ゆらぎを作り、そのゆらぎはどのように時間進化をするのかを求めた。そしてこの模型に基づく暗黒物質の崩壊現象が観測量に与える影響としてCMBの温度ゆらぎのパワースペクトルと物質のパワースペクトラムに与える影響を計算した。
本発表ではこれら一連の計算結果を発表する。
Speaker
John Silverman
Date/Place
13:30-, 18(Thu), Oct. @ES606
Title
Environments of Active Galaxies from large-scale
structures to their host bulge
Abstract
I will present results from our study of the
mechanisms likely responsible for the buildup of supermassive black holes with cosmic
time. In particular, we investigate how Active Galactic Nucleus activity is related to
their host galaxies, presence of nearby neighbors, and the large scales structures in
which they reside. I will also discuss how supermassive black holes and their host
galaxies may migrate onto local mass relations. I may touch upon similar studies with
future surveys using Subaru/FMOS, HSC and PFS.
Speaker
Hayato Shimabukuro
Date/Place
13:30-, 24(Wed), Oct. @ES606
Title
Probing minihalo
abundance with 21cm absorption
Abstract
ビッグバンから約38万年後、それまで電離ガス状態であった宇宙の物質は中性化し、それからしばらく光を放つ天体の存在しない暗黒時代が続いた。その後、密度揺らぎが成長し、初期の天体が形成された。暗黒時代の観測は現在の技術では困難だが、今後、発展が期待される電波観測で可能になると考えられている。そこで本研究では、暗黒時代に存在するミニハローと呼ばれる初期天体による21
cm線電波の吸収に注目する。ミニハローとは、暗黒物質と水素ガスが重力収縮したものの、ビリアル温度が低いため、効率的に冷却せず銀河になることができなかった、初期銀河に比べて軽い天体である。
本研究では、ミニハローの光学的厚さに最も影響を与えるスピン温度や中性水素ガスの密度を計算し、吸収の度合いを表すミニハローの光学的厚さと存在個数の関係を求めた。また、インフレーションによって生成される初期のパワースペクトルや、ニュートリノの質量が存在個数に与える影響を計算した。
Seminars in November
Speaker
Daichi Kashino
Date/Place
13:30-, 1(Thu), Nov. @ES606
Title
Subaru/FMOS survey of star forming galaxies at z ∼ 1.5
in COSMOS
Abstract
It has become clear that in the epoch of z ~ 1-3 the
star formation rate density became highest in the cosmological time scale. Crucial steps
forward are to clarify what drive star formation in galaxies in this epoch and to
disentangle relations between the star formation rate of galaxies and both internal and
external properties, such as their mass, environment, metallicity and so on.
Subaru/FMOS(Fiber Multi-Object Spectrograph) enables us to spectroscopically survey ~200
galaxies at an exposure in the near-infrared band. Some strong emission lines such as
Halpha and [Nii] are falling within the NIR window if the galaxy exists at z ~ 1.5. We
observed ~600 photo-z selected galaxies in the COSMOS field at an epoch (1.4 <~ z <~
1.7) of rapid galaxy formation, and obtain spectra of roughly 140 galaxies for which
fiducial Halpha emissions have been detected. From these spectra, we obtain the
accurate redshift and measure the star formation rate based on the Halpha line flux
and the ratio of [Nii]/Halpha less impacted by dust extinction. In this talk, we
overview our project, show the relation between the star formation rate of galaxies
and their existing stellar mass, and discuss the galaxy evolution at this
period.
Speaker
Toyokazu Sekiguchi
Date/Place
13:30-, 8(Thu), Nov. @ES606
Title
Axion CDM from axionic string-wall system
Abstract
Axion is a Nambu-Goldstone boson of the anomalous
U(1) Peccei-Quinn (PQ) symmetry, and one of the promising candidates of cold dark matter
(CDM) in the Universe. In the early Universe, spontaneous breaking of the U(1) PQ
symmetry generates a network of axionic strings and domain walls. Axion can be copiously
generated from the string-wall system and can over-close the observed CDM abundance.
Based on the field theoretic simulations of the PQ scalar field, we estimate the
abundance of axions from the system and present an updated constraint on the axion decay
constant.
Speaker
Naonori Sugiyama
Date/Place
13:30-, 22(Thu), Nov. @ES606
Title
Nonlinear dark matter power spectrum beyond BAO scale
Abstract
近年、ダークマターパワースペクトルから宇宙の進化や構造における情報を取り出そうという試みが盛んに行われている。特に、パワースペクトル内のバリオン音響振動(BAO)の観測は、宇宙論パラメータの制限を与える新たな手法として注目されており、そのための理論的な研究が盛んに行われて来た。
本研究では、ダークマターパワースペクトルの非線形進化について、BAO
スケールを超えたよりスモールスケールにおける振る舞いを調べる。そのためにまず、現在最も精度のよい予言を与えるとされるReg
PTという近似法を、標準摂動論のカーネル関数の近似を用いて導出し、さらにはその拡張を考える。その結果、従来の理論的研究では計算する事のできなかったスモールスケールにおけるダークマターの振る舞いを記述することに成功した。
Seminars in December
Speaker
Tsutomu T. Takeuchi
Date/Place
13:45-, 20(Thu), Dec. @ES606
Title
Recent topics on the IRX-beta relation: still a
convenient tool to fight with dust attenuation?
Abstract
The star formation rate (SFR) of galaxies is one of
the fundamental physical quantity for understanding the formation and evolution of
galaxies. At high redshifts (z > 3), usually the SFR is measured by the ultraviolet (UV)
continuum of galaxies because of the low observational cost. However, the UV continuum
is very sensitive to dust attenuation. The most direct method to overcome this problem
is to measure the SFRs directly visible at UV and that measured through the far-infrared
(FIR) dust emission from dust, since the latter represents the UV luminosity absorbed by
dust. The difficulty of this method is that the FIR measurement is still a difficult
task at z > 3. Then, a convenient method to correct dust attenuation without IR
measurement was longed for. Meurer et al. (1999) showed a tight relation between the UV
spectral slope (beta) and the luminosity ratio between UV and IR (infrared excess: IRX),
and proposed the method to estimate the IRX only from beta. Since this requires only the
UV measurements, it became very popular among high-z galaxy researchers. However, many
authors examined the relation itself and found that the relation does not always
hold.
In this talk, I report some recent progress on the understanding of the IRX-beta
relation, and show the latest result on its evolution.
Seminars in January
Speaker
Shohei Saga
Date/Place
13:30-, 17(Thu), Jan. @ES606
Title
Generation of
magnetic fields in Einstein-Aether gravity
Abstract
現在、宇宙には小スケールから銀河や銀河団といった大きなスケールまで磁場が存在していると考えられている。この起源の候補として、今回我々は初期宇宙における原始プラズマのゆらぎによる生成に注目した。初期プラズマでは光子が陽子と電子と頻繁に衝突しているが、電子の方が陽子より押されるため電場が生じ、磁場も作られる。これを可能にするには1次の摂動を考えた場合ベクトルモードが存在する必要がある。ところが標準的な宇宙論的摂動論には、ベクトルモードが存在しないと考えられている。
一方で、量子重力をモチベーションとするアインシュタイン-エーテル理論には今までにないベクトル場(エーテル)が存在する。そのため、エーテルによるベクトルモードが存在する。我々は、このベクトルモードにおける初期プラズマ中の磁場生成について議論したのでその結果を発表する。
Speaker
Yuki Shibusawa
Date/Place
13:30-, 17(Thu), Jan. @ES606
Title
Cosmological
Spherical Collapse with Magnetic Field
Abstract
宇宙空間には地球から銀河、銀河団など様々なスケールで磁場が存在しているが、このような磁場がどのように生成され、進化してきたかについてはまだ理解されていない。また、磁場は宇宙の構造形成において大きな影響を及ぼし、様々な天体現象を解明する上で重要な手がかりとなっている。
今回は構造形成に着目した。シンプルな構造形成のシナリオであるspherical collapse
modelにおいて磁場をローレンツ力として加え、構造形成の閾値であるcritical
overdensityを求めることで磁場が構造形成に与える影響について考察した。さらにその値を用いてredshiftごとのhalo mass
functionを計算した。これらの計算結果について議論する。
Speaker
Yoshiki Matsuoka
Date/Place
13:30-, 24(Thu), Jan. @ES606
Title
Probing high-z
super massive black holes by Subaru/Hyper Suprime-Cam
Abstract
現在の宇宙には、太陽の100万倍から10億倍にも達する質量を持った超巨大ブラックホールが普遍的に存在することが知られている。これらがいつ、どこで、どのように形成されたのかを知ることは、天体・構造形成史を理解する上で不可欠な課題の1つであり、過去の宇宙の探査によってその手がかりを得ることが待望されている。また超巨大ブラックホールの一部は活動銀河核
(AGN)
現象によって極めて明るく輝くため、遠方宇宙の貴重な灯台として利用することができる。特に再電離や初期星形成史などの測定は、暗黒時代直後の宇宙進化を理解する上で重要なテーマである。
今回のセミナーではこれらの話題に簡単に触れるとともに、すばる望遠鏡の新観測装置Hyper
Suprime-Camによってまもなく開始予定の遠方超巨大ブラックホール探査について紹介する。
Seminars in February
Speaker
Shinsuke Asaba
Date/Place
13:30-, 5(Tue), Feb. @ES606
Title
Constraining models
of modified gravity by the principal component analysis
Abstract
最近の観測から、宇宙が加速膨張していることがわかっている。加速膨張を説明する理論として、ダークエネルギーと修正重力理論があるが、そのどちらが正しいかを決めることは、宇宙論の大きな課題の一つである。
今回は、将来的な重力レンズと銀河の固有運動の観測から、修正重力理論に対してどの程度制限できるかについて発表する。本研究では、修正重力理論の関数形を仮定せず、波数-レッドシフト空間をグリットに分け、各グッリト上でパラメーターを設定するというモデルを考える。また、パラメーターの数が多いため、主成分分析を行い、どのようなモードが制限されやすいかについて議論する。
Speaker
Yoshitaka Takeuchi
Date/Place
13:30-, 28(Tue), Feb. @ES606
Title
ヘリウム-3からの超微細構造線
Abstract
中性水素の超微細構造の遷移に起因するスペクトル線は、それに対応する波長の長さから
21cm-線として良く知られている。しかし、中性水素以外にも超微細構造を持つ原子は存在し、同位体ヘリウム(ヘリウム−3)もその中の一つであり、より厳密には一価のヘリウム−3が超微細構造を持っている。近傍の宇宙では中性水素がほぼイオン化されてしまっていることから、IGM中の中性水素の割合は極端に低くなってしまっている。一方で、ヘリウム−3はイオン化された状態で多数存在していると考えられる。よって、ヘリウム−3には中性水素では観測が難しいような近傍宇宙を探ることのできる可能性を秘めている。ここでは、中性水素の場合と比較しながら、近傍宇宙でヘリウム−3からの超微細構造線が将来、あわよくば既存の電波望遠鏡で観測可能かを議論したい。