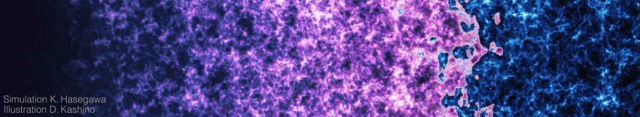4月のセミナー
発表者
飯田 遼
日程/場所
4月14日(木)13:00-@ES606
概要
宇宙背景輻射(CMB)の発見により、ビッグバン理論は宇宙の進化を記述する揺るぎない理論となった。しかし、地平性問題や平坦性問題といわれるいくつかの問題はビッグバン理論だけでは説明ができない。インフレーション理論はビッグバン理論が残した諸問題を解決しうるものであり、近年の宇宙観測の発展によりますます有力な理論となってきている。インフレーション期は超高エネルギー期であるため、インフレーション宇宙の痕跡を探ることにより、究極の理論と期待されている超弦理論の検証を行うことが可能であると期待される。今回、超弦理論における重要な双対性であるモジュラー不変性を持つインフレーションモデルを用いて初期ゆらぎのパワースペクトルを求める数値計算を行った。そしてその結果を用いてCMBでの観測との比較、検証を行った。本発表ではこれら一連の研究について報告する。
発表者
角田 匠
日程/場所
4月14日(木)13:00-@ES606
題名
Massive-neutrinoが構造形成に与える影響
概要
宇宙の晴れ上がり以前は光子とバリオンが混合流体となって運動をしており、光子の持つ圧力によって混合流体のゆらぎが音波モードとなって振動します。これをバリオン音響振動といいます。晴れ上がり後はバリオンの音響ピークが100h^{-1}Mpc
にとどまり、そこにダー クマターが引き寄せられて特徴的なスケールをもつゆらぎとなります。massive-neutrino に関しても特徴的なスケールに clustering
していた場合に、同じようにダークマターが引き寄せられるのではないかと今回私は考えました。点状の初期密度ゆらぎの発展を数値計算し、massive-neutrino
が非相対論的になった後にダークマターやバリオンが集まってくるのかを確かめてみました。また、より現実的なニュートリノモデルとして sterile-neutrino
についても同様に数値計算をしてみました。それらの数値計算の結果と2点相関関数から massive-neutrino がどれくらい構造形成に影響を与えるのか結果を報告します。
発表者
竹内 太一
日程/場所
4月14日(木)13:00-@ES606
題名
銀河合体における力学的摩擦による超巨大質量ブラックホール成長の検証
概要
現在の宇宙には巨大銀河や大質量ブラックホールが存在し、銀河のバルジ質量とその中心のブラックホール質量の間に比例関係があることが指摘されている(e.g., Kormandy &
Ho
2013)。銀河は階層的構造形成モデルに従って進化すると考えられている。銀河同様に超巨大質量ブラックホールも合体によって成長したとすれば、上記の関係を自然と説明できる可能性があるが、ブラックホールが銀河中心に落ちる為には、その角運動量を失う必要がある。ブラックホールが角運動量を失う物理過程の一つとして、力学的摩擦があげられる。本研究では力学的摩擦を数値計算で解くことで、銀河合体における超巨大ブラックホールの成長を力学的摩擦で説明できるかどうかを検証した。その結果、質量が
10^8 Msun以上のブラックホール同士であれば、力学的摩擦によって宇宙年齢以内で合体することが可能であるという結果を得た。
発表者
田中 俊行
日程/場所
4月14日(木)13:00-@ES606
題名
The epoch of
reionization: Could first stars contribute even just a little bit?
概要
In concordant cosmological models, first stars began to form at a redshift z~30 and
subsequently galaxies and active galactic nuclei were born. These luminous objects in
the early universe ionized intergalactic medium by z~6. However, the relative
contributions are largely controversial. Based on a simple analytic model of ionizing
sources, we calculate the evolution of HI fraction and the optical depth to Thomson
scattering of CMB photons, and compare them with observations by Planck. As a result, we
find that first stars contribute about 0.01 to the optical depth.
発表者
杉山 直
日程/場所
4月21日(木)13:00-@ES606
題名
年度頭所感
概要
年度頭所感
発表者
箕田 鉄兵
日程/場所
4月21日(木)13:00-@ES606
概要
ハドロンを構成する主な素粒子はクォークという物質粒子とクォーク同士に働く力を媒介するグルーオンというゲージ粒子である。我々の日常的な温度スケールではクォークとグルーオンはハドロン内部に強く閉じ込められているが、高温度及び高密度の極限状態では相転移を起こ
し、クォーク・グルーオン・プラズマ (QGP) という物質相があらわれる。このような物質はビッグバン直後の初期宇宙に存在していたと考えられている。QGP
のダイナミクスを記述する相対論的流体力学では、方程式が非線形となるために数値計算が不可欠である。近年では実験の精
度が向上してきたために数値計算においても高精度な手法が用いられるようになってきた。そこで本研究では非相対論的流体力学の分野で用いられてきた CIP
マルチモーメント法を相対論的流体力学に適用し、解析解との比較を行うことによりCIP 法の有用性を考察する。
発表者
簑口 睦美
日程/場所
4月21日(木)13:00-@ES606
題名
相対論的Zel’dovich近似に基づくヴォイドの進化
概要
宇宙の構造形成において、銀河など密度が高くなる系においては系の大きさは大きくならないが、ヴォイドのような空虚な構造は宇宙の膨張とともに大きくなり、100Mpc
を超える構造が存在する。近年の精密観測により、相対論的効果も観測可能になってきている。このような状況で、巨大ヴォイドの進化の相対論的効果を解析するのは、重要な課題と考える。そこで本研究では巨大ヴォイドの時間発展について、Newton的宇宙論に基づく解析と相対論的効果を取り入れた解析を比較する。それにより、相対論効果がヴォイドの進化や構造にどの程度の影響を与えるかを調べる。
発表者
嵯峨 承平
日程/場所
4月28日(木)13:00-@ES606
概要
前回の発表では2次の摂動によって引き起こされるベクトルモード(また、テンソルモード)のCMBレンジングと銀河のコスミックシアーの観測可能性について発表した。その結果は、現在・将来観測ともに観測不可能であることを示したのみであった。しかし、一つ重要な帰結として、原始重力波のテンソルスカラー比が0.1程度であれば、2次のベクトルモードがそれと同じくらい匹敵するということがわかった。この傾向は現在に近づけば顕著になると考えられる。そこで、今回は21cmレンジングを用いた場合の観測可能性について議論するが、その途中経過に関して報告したい。
5月のセミナー
発表者
柏野 大地
日程/場所
5月12日(木)13:00-@ES606
概要
星間物質 (ISM)
の性質は、銀河の過去の進化史と現在の活動を反映している。高赤方偏移銀河は、高い星形成率及びそれを支える高いガスフラクションなど、近傍の銀河ことは大きく異なる様子が見せる。このことから、ISMの性質も近傍の銀河とは様々な点で異なっていることが予想される。我々は、赤方偏移z~1.6の星形成銀河の星形成領域のガスの状態を、経験的な輝線診断法に基づいて調べ、近傍銀河に比べて、ガス密度が高いこと、励起状態が高いこと、金属量が小さいことなどを明らかにした。これらの結果を報告する。
発表者
淺羽 信介
日程/場所
5月18日(木)10:30-@ES606
概要
標準宇宙論モデルは宇宙マイクロ波背景放射や大規模構造の観測結果を説明することに成功した。その一方で、小スケールの構造形成についての議論は不完全である。近年、宇宙晴れ上がり時に存在するダークマターとバリオン間に存在する超音速相対速度の重要性が示唆された。本研究では、球対称崩壊モデルを拡張することで超音速相対速度が小スケールの構造形成に与える影響のモデル化を行った。その中で、環境効果を考量した結果について報告する。また、現在行っているSPHシミュレーションを用いたminihaloに関する研究についても紹介する。
発表者
小林 将人
日程/場所
5月25日(木)10:30-@ES606
概要
近年の大規模な電波観測から,近傍銀河において巨大分子雲質量関数が銀河の領域ごとに異なるスロープを持つ,ということが示され始めた(e.g., Colombo et al.
2014).
分子雲は星形成の種であるので,銀河スケールでの巨大分子雲質量関数のスロープを,何が如何に統御しているかを明らかにすることは,星形成やそれに続く銀河進化を理解する鍵と言える.Inutsuka
et al. 2015 にて,超新星残骸や大質量星の HII 領域が膨張することに伴い銀河円盤を埋めている warm neutral medium
が多数回圧縮され分子雲が形成される,という分子雲形成描像が提唱された.今回我々は,この Inutsuka et al. 2015
の描像を基にして,巨大分子雲質量関数の時間発展方程式を再定式化した.この再定式化では,近年大質量形成機構として注目されている分子雲同士の衝突も考慮した.本発表では,
時間発展方程式の数値積分結果から,観測と比較することで銀河スケールでの分子雲の形成・散逸に関する制限が得られるという知見を得たのでこれを紹介する.さらに,散逸により星間空間へ還元されるガスが,最小質量巨大分子雲の生成に寄与する割合を評価し.巨大分子雲質量関数の時間発展が3フェーズに分類されることを見出したので,これを報告する.最後に銀河中心への応用や星団形成理論への展望も述べる.
発表者
石山 智明 (千葉大学)
日程/場所
5月26日(木)10:00-@ES606
題名
スーパーコンピュータによる構造形成シミュレーション [1] [2] [3]
概要
宇宙論的シミュレーションはダークマターハローの構造や分布を知る上で必須のツールである。我々はスーパーコンピュータ上で大規模シミュレーションを実現し、データの二次利用を促進する体制を構築するとともに、最小スケールから大規模構造までの全スケールのハローの構造や分布を明らかにしてきた。今回は特に、小スケールのハローのダークマター対消滅シグナルへの寄与についてや、ミニハローの中で生まれ現在まで生き残った初代星の観測可能性などについて議論する。
6月のセミナー
発表者
堀口 晃一郎
日程/場所
6月1日(水)10:30-@ES606
題名
Oscillations in
the CMB angular power spectra at ell ~ 120
概要
宇宙マイクロ波背景放射(CMB)はWMAP衛星の観測で温度揺らぎのスペクトルが観測されて以来、初期宇宙に迫る観測として標準宇宙論の枠組みでは多くの成功をおさめてきた。しかし、WMAP衛星の時代からmultipole
: ell ~
120付近に標準宇宙論では説明できない振動があることが示唆されてきた。近年ではPlanck衛星等により、より精密なCMB観測が進められているが、Planck2015の観測にもWMAPで示唆されていたmultipole
: ell ~
120付近でCMB角度パワースペクトルの振動が表れていることが判明した。本発表では、Planck2015の観測に現れる振動の位置や大きさなどの解析結果をWMAPの場合と比較して紹介する。
発表者
大場 淳平
日程/場所
6月8日(水)10:30-@ES606
概要
超弦理論が想定する高次元重力理論からは、一般相対性理論を極限に持つような様々な修正重力理論が示唆されており、観測からこれらを制限することは重力理論の解明のために非常に重要である。そこで、修正重力理論と一般相対性理論とのずれをモデルパラメータで記述し、観測結果を用いて制限を与える。本研究では、修正重力理論のモデルとしてスカラーテンソル理論に着目し、Planck衛星による宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の温度揺らぎ、偏光、レンジングの観測データを用いて、モデルパラメータへの制限を行った。また、スカラーテンソル理論は、観測される重力定数が時間発展するという特徴を持っているので、現在の重力定数とCMBが放射された時代の重力定数とのずれについてもモデルパラメータへの制限と同様にして制限を与えた。それらの結果に加えて、制限に用いたマルコフ連鎖モンテカルロ法におけるパラメータの選び方が結果に与える影響についても議論する。
発表者
新居 舜
日程/場所
6月15日(水)10:30-@ES606
概要
ローレンツ対称性は、重力を含まないミクロな世界を記述する素粒子理論における基本的対称性であり、重力法則を考える場合でも一般に局所ローレンツ対称性を仮定する。これまでのところ、電磁理論においてローレンツ対称性が破れている兆候はないが、重力理論そのものが局所ローレンツ性を必ず満たす否かは実は自明ではない。実際、2009年にP.Horavaが提唱したHorava-Lifshitz重力理論(HL重力理論)では、局所ローレンツ性を破る代わりに重力理論がくりこみ可能となり、さらには宇宙論とも整合性を保つ重力模型も存在することが示された。そこで、重力理論がローレンツ対称性をや保つか否かを観測検証することは、重力法則を解明する上で非常に重要な課題である。本発表では、重力理論においてローレンツ対称性が破れている場合に起こる2つの現象を研究した結果を報告する。1つ目の研究はHL重力理論で記述される時空上でインフレーションを起こし、インフレーション中に生成される初期密度揺らぎの研究である。HL重力理論では時間と空間の非対称性により揺らぎのスカラー自由度(スカラーグラビトン)が存在するが、先行研究ではスカラーグラビトンを無視されていた。我々の研究ではスカラーグラビトン整合的に考慮した初期曲率揺らぎの生成過程について正確な描像を与えた。その結果、通常の断熱揺らぎが生成した後も、スカラーグラビトンの揺らぎがエントロピー揺らぎとして不安定成長することが明らかとなった。また、原始重力波のスペクトラムを測定することで、スカラーテンソル比や無矛盾性関係からインフレーションの起こるエネルギースケールでローレンツ対称性を検証できることを示した。2つ目の研究はCMB
distortionを用いたローレンツ対称性の新たな検証方法である。重力理論がローレンツ対称性を破る簡単な重力模型を用意し、脱結合後の光子の分布関数の時間進化を調べた。その結果、脱結合後の光子の赤方偏移進化がエネルギーに依存するためにCMB
distortionが生じることを示した。最後に、2つの結果を踏まえてローレンツ対称性の破れを観測的に検証する方法について議論する。
発表者
遠藤 隆夫
日程/場所
6月15日(水)10:30-@ES606
題名
ダークエネルギーの揺らぎがボイド形成に与える影響について
概要
ダークエネルギーは宇宙の加速膨張の原因の候補と考えられており、その性質の解明は現代宇宙論における最大の課題の一つである。本研究では、ダークエネルギーの密度・圧力が空間的に揺らいでいると仮定し、この揺らぎが宇宙大規模構造の中のボイドに与える影響を調べることでダークエネルギーの性質に迫ることを目的としている。前回1月の発表では、ダークエネルギーの揺らぎを取り入れた球対称崩壊モデルを紹介した。その中で、先行研究において、ダークエネルギーの状態方程式パラメータと音速を変えることによって、ダークエネルギーの揺らぎの成長の仕方が変化し、崩壊までの時間スケールが変化する結果が得られたことを報告した。本研究では先行研究の方法を球対称に時間発展するボイドに応用した。その結果、ダークエネルギーの揺らぎはボイド形成へも影響を与えることが判明した。本発表では、この結果に加え、ダークエネルギーの揺らぎがボイドのサイズ分布(Sheth
and Weygaert (2004))へ与える影響も報告する。
発表者
堀井 俊宏
日程/場所
6月22日(水)10:30-@ES606
題名
大規模構造のフィラメントにある中性水素21cm線シグナル
概要
宇宙マイクロ波背景放射から予言されるバリオン質量のほとんどは未だ直接検出されておらず、これはミッシングバリオンと呼ばれている。観測的には未検出ではあるが、理論的にはミッシングバリオンの候補の一つとして、Warm
Hot Intergalactic Medium (WHIM) と呼ばれる大規模構造のフィラメント部分に存在しているバリオンガスが考えられている。
本研究では、中性水素の超微細構造遷移に伴う21cm線に着目し、これを用いたWHIMの直接検出の可能性の検証を行った。先行研究であるTakeuchi et al.
(2014)では、現在の観測機器でも21cm線シグナル検出が可能であると結論づけていたが、N体計算による物質分布と単純なガス温度進化計算モデルを使用しており、シグナル強度の見積もりが正確でない可能性があった。それに対し本研究では、バリオンの密度や温度をより正確に計算している宇宙論的流体シミュレーションIllustris
(Genel et al. 2014; Vogelsberger et al. 2014)
のデータの解析から21cm線シグナル強度を見積もり、宇宙再電離期から現在までの21cm線の検出可能性を調査した。その結果、フィラメント部のガスは先行研究の見積もりより高温である事がわかり、結果として中性水素割合・21cm線輝度温度が小さくなる事を示した。この結果をもとにSKAによるWHIM検出可能性についても議論する。
発表者
松井 由佳
日程/場所
6月22日(水)10:30-@ES606
概要
位相欠陥の一種であるcosmic stringはひも状の高エネルギー領域である。cosmic string同士は衝突し、kinkと呼ばれる尖りが生成される。そしてcosmic
stringはkinkから重力波を放出し、背景重力波を形成する。 本研究ではkinkの分布を計算し、kinkから放出される背景重力波のpower
spectrumを求め、その背景重力波の将来観測可能性について報告する。 kinkから放出される背景重力波は、kinkの分布に依存している。Kawasaki et al.
(2010)のkinkの分布は、輻射優勢期に生成されたkinkの数を過小評価していた。そこで我々は、数値計算を用いてkinkの分布の正確な見積もりを行い、背景重力波のスペクトルを見積もり直した。kinkの分布では、輻射優勢期に生成されたkinkの数と物質優勢期に生成されたkinkの数に大きな違いが生じ、それに伴って背景重力波のpower
spectrumも変化した。以上から、将来観測計画のある重力波干渉計のeLISAやDECIGO、電波干渉計のSKAでの観測可能性を議論する。
発表者
松原 隆彦
日程/場所
6月29日(水)10:30-@ES606
概要
宇宙論的大規模構造解析において、銀河バイアスの理解は重要な課題である。最近では、いくつか有望なバイアスの解析的モデルが提案されている。ここで、観測量がどのようにバイアスに依存するのかを知る必要がある。統合摂動論の枠組みにより、準非線形領域における観測量のバイアス依存性を一般的に調べることが可能になったので、今回は代表的ないくつかのバイアスモデルに対する結果を示す。一般的に、準非線形領域におけるバイアスの不定性はそれほど大きくないことがわかったが、パーセントレベルの影響を問題にするときには、バイアス機構の精密なモデル化が必要となる。
7月のセミナー
発表者
市來 淨與
日程/場所
7月6日(水)10:30-@ES606
題名
B-mode検出にむけたデルタマップ方による前景放射除去
概要
インフレーション重力波起源のB-mode偏光を検出するためには、天体起源の強烈な前景放射を除去しなければならない。とりわけ、銀河系からのシンクロトロン放射およびダストによる熱放射は、銀河系磁場にそって大角度スケールに渡り揃った偏光を持ち、近年のプランク、BICEP2実験の結果からインフレーション重力波起源のB-modeを完全に隠していることが明らかになっている。従って、前景放射はその周波数依存性および分布の統計的性質がCMBとは異なっているという情報を上手に用いてその放射を除去するための様々な手法が開発・提案されている。
セミナーでは前景放射の特徴をCMBのB-mode偏光シグナルと比較し、インフレーション重力波の検出に向けた前景放射除去に対する要求をまとめる。その中で、LiteBIRD
Working
Groupによって開発&改良中の前景放射除去アルゴリズム「デルタマップ法」を紹介し、この手法による前景放射除去シミュレーションの結果を示す。「デルタマップ法」は、2011年に発表した片山\&小松(ApJ737,
78,
2011)による方法を、前景放射スペクトルの巾の方向依存性まで対応できるように拡張したものである。結果を元に、B-mode偏光検出によるインフレーション理論検証への期待と問題点を議論したい。
発表者
黒柳 幸子
日程/場所
7月13日(水)10:30-@ES606
題名
Anisotropies in
the gravitational wave background as a probe of the cosmic string network
概要
真空の相転移や超弦理論から予言される1次元の位相欠陥「宇宙ひも」は、その運動から強い重力波を放出する。将来の重力波
実験で宇宙ひもの存在を検証することが可能になれば、その生成機構や関連する初期宇宙物理に示唆が得られることが期待される。本セミナーではSKAなどの電波望遠鏡を使ったパルサータイミングによる重力波検出の取り組みについて話し、背景重力波の非等方性を新たな観測量として宇宙ひもの情報を得るのに役立てるための研究を紹介する。
8月のセミナー
9月のセミナー
発表者
Cheng Cheng
日程/場所
9月28日(水)16:00-@ES606
題名
Numerical research of
the early universe with CMB data sets
概要
CMB is the earliest information we can get from the universe. An exciting result we get
from the CMB observation results is that the scalar fluctuation is adiabatic, which
indicates the success of the inflation scenario. But still, there are too many inflation
models. Things we can do next step is to characterize features of inflation era. And the
purest information we can get from the early time to investigate is primordial
gravitational waves. So, extracting the information of tensor perturbation encoded in
CMB data is an interesting work. During my PhD, I’m focus on the numerical cosmology,
especially on the CMB data analysis, which is getting the information from the early
time to distinguish different inflation models. In this talk, I will briefly introduce
the constrain on inflation model with the latest CMB data sets, and if time permits, I
will introduce a work about CMB parity asymmetry.
10月のセミナー
発表者
西澤 淳
日程/場所
10月6日(木)10:00-@ES606
題名
Self-Organizing-Map
and Deep-Learning - Application to the photometric redshift in HSC -
概要
人工知能の発展の中で、未知の量を既知データをもとに推定する機械学習という分野が発展してきた。
自己組織化マップ(SOM)もその一つで、一般に教師データを必要とする機械学習とは異なり、 教師なしで学習する機能を有する。また機械学習の走りであったNeural
Networkを多層化した Deep Learningは今日ではGoogleの画像検索やSNSなどあらゆる場面で利用されている。
一方、天文学の分野では20年程前から機械学習が取り入れられており、主に測光的赤方偏移 (photo-z)の推定に応用されてきた。
本セミナーでは、SOMの原理を説明した後、HSCデータを用いてphoto-zに応用した結果をお見せする。
photo-zは基本的には観測量である銀河のfluxやflux比が持ちうるほぼ全ての情報であり、
伝統的なテンプレートフィット、様々な種類の機械学習を用いても、その持ちうる情報量にリミットされてしまう。
そこで、銀河の空間的なclustering情報を付加することで、photo-zとは独立な銀河の距離推定を行うことができる。
SOMはもともとデータのclassificationに長けており、その特徴を用いて、Rahman+2015などの手法を拡張する。 最後に、Deep
Learningによるデジタル画像そのものからphoto-zを推定する方法についても紹介する。
発表者
新田 大輔
日程/場所
10月13日(木)10:00-@ES606
概要
宇宙ひもは、宇宙論的規模で相転移が起こる際に現われ得る位相欠陥で、高密度なひも状の物体である。まっすぐな宇宙ひもまわりの時空の特徴は、欠損角はあるが曲率がないことである。しかし実際には、ひもの生成時の状態に依存して、形状には微小な構造(ウィグル)があり、それによって曲率を作っていると考えられる。この曲率は物理的に離れた2点間に潮汐力を引き起こす。したがって、レーザー干渉計を用いて宇宙ひもの存在を確かめられる可能性がある。
本研究では、レーザー干渉計宇宙アンテナ(LISA)を用いた、ウィグルのある宇宙ひもとループ状のひもが引き起こす潮汐力の検出可能性について調べた。結果、ウィグルがある場合、ひもの張力に依存するがLISAから数十パーセクの距離にあるものなら検出可能であることがわかった。今回の発表でそれらの結果を報告する。また、宇宙ひもが放出する重力波とどちらが検出しやすいのかも議論する。
発表者
田代 寛之
日程/場所
10月27日(木)10:00-@ES606
題名
宇宙再電離期の磁場生成
概要
銀河団や宇宙大規模構造で観測されている磁場の起源は未だ理解されていない。さらに近年、高エネルギーガンマ線の観測から、宇宙には非常に微弱な磁場が満ちている可能性も指摘された。このような状況の中、これら磁場の起源として、宇宙論的種磁場生成シナリオが大きく注目を集めている。
今回のセミナーでは、宇宙論的シナリオの一つである宇宙再電離期における種磁場生成に注目する。星からの輻射を受け銀河間物質にcharge
separationが生じ、そのため磁場生成がなされるのである。最近の数値計算を用いた量的評価の研究を紹介した後、これを簡単な宇宙再電離モデルに適用し、どの程度の磁場が生成されるかを議論する。
11月のセミナー
発表者
新居 舜
日程/場所
11月10日(木)10:00-@ES606
概要
Lorentz対称性は、重力を含まないミクロな世界を記述する素粒子理論における基本的対称性であるが、重力法則を考える場合は等価原理から局所Lorentz対称性を仮定する。しかし、重力理論そのものが局所ローレンツ性を必ず満たす否かは実は自明ではない。実際、2009年にP.Horavaが提唱したHorava-Lifshitz重力理論(HL重力理論)では、一般相対性理論がくりこみ不可能であることに対して、局所Lorentz対称性を破ると自然に重力理論がくりこみ可能となることがわかっている。それゆえ、重力理論がLorentz対称性をや保つか否かを観測検証することは、重力法則を解明する上で非常に重要な課題である。
本発表では、重力理論におけるLorentz対称性が破れている場合に起こる宇宙論的な2つの現象を研究した結果を報告する。1つ目の研究はHL重力理論で記述される時空上でインフレーションを起こし、インフレーション中に生成される初期揺らぎの研究である。HL重力理論ではLorentz対称性を破ることで重力のスカラー自由度(スカラーグラビトン)が存在する。スカラーグラビトンがインフラトンと結合する場合の初期曲率揺らぎの生成過程について正確な解析をした結果、断熱揺らぎはインフラトンにより決まりスカラーグラビトンは初期密度ゆらぎを生じないことがわかった。さらに、Lorentz対称性がない場合にはスカラーとテンソルゆらぎの間の無矛盾性関係が破れることがわかった。この結果を応用すると、将来原始重力波が観測された際にインフレーション期にLorentz対称性の破れを直接検証できることになる。2つ目の研究はCMB
distortionsを用いたLorentz対称性の新たな検証方法である。一様等方時空重力理論がLorentz対称性を破る簡単な重力模型を用意し、脱結合後の光子の分布関数の時間進化を調べた。その結果、脱結合後の光子の赤方偏移進化がエネルギーに依存するためにCMB
distortionsが生じることを示した。最後に今後の研究の展望について話す。
発表者
遠藤 隆夫
日程/場所
11月10日(木)10:00-@ES606
概要
宇宙の加速膨張を担うとされるダークエネルギーの解明は、現代宇宙論における最大の課題の一つである。ΛCDMモデルは空間的に一様なエネルギー密度を持つダークエネルギーを仮定し、現在標準的なモデルとなっているが、そのエネルギーの源についてはわかっていない。
本研究ではダークエネルギーのモデルを一般化してボイド内部におけるダークエネルギーの密度揺らぎの成長を計算し、この揺らぎがボイド形成の時間発展に与える影響を見積もった。本発表ではダークエネルギーのモデルを特徴付けるパラメータとしてダークエネルギーの音速、状態方程式パラメータを変化させた際の、ボイド内部におけるダークエネルギーの揺らぎ成長の仕方及び、ダークエネルギーの揺らぎがボイドの成長に与える影響を報告する。
発表者
松井由佳
日程/場所
11月17日(木)10:00-@ES606
題名
The gravitational
wave background from kinks on infinite strings
概要
位相欠陥の一種であるcosmic stringは、stringの傾きが不連続な領域であるkinkと呼ばれる尖った構造を有している。
そしてcosmic stringはkinkの運動を通して重力波を放出し、背景重力波を形成することがDamour and Vilenkin (2001)などで示唆されている。
そしてこの背景重力波は正確に見積もられている(Kawasaki et al. (2010), Matsui et al. (2016))。
一方、超弦理論由来のcosmic
superstringにはY-junctionと呼ばれる三叉路構造があり、これはkinkの分布を変化させることが知られている(Binetruy et al. (2010))。
これにより、cosmic stringによる背景重力波のpower spectrumは変化すると期待されている。今回我々はcosmic
stringのネットワークの進化からY-junctionに入射するkinkの割合を計算し、それに伴うkinkの分布の変化を求めた。そしてY-junctionを持つstringから放出される背景重力波のpower
spectrumを求めた。
また、cosmic superstringはstring同士が衝突して組み換わる確率が低いことが期待されている(Polchinski
(2004))。今回、この組み換え確率も変化させた背景重力波のパワースペクトルも求めた。infinite string上のkinkから放出される重力波について報告する。
発表者
堀井俊宏
日程/場所
11月17日(木)10:00-@ES606
題名
ミッシングバリオン問題
-中性水素21cm線による挑戦-
概要
宇宙マイクロ波背景放射から予言されるバリオンのおよそ半分は、未だ直接検出されておらず、これはミッシングバリオンと呼ばれている。観測的には未検出であるが、理論的にはミッシングバリオンの候補の一つとして、Warm
Hot Intergalactic Medium (WHIM) と呼ばれる大規模構造のフィラメント部分に存在するバリオンガスが考えられている。
本研究では、中性水素の超微細構造遷移に伴う21cm線に着目し、これを用いたWHIMの直接検出の可能性の検証を行った。具体的には、宇宙論的流体シミュレーションIllustris
のデータの解析から21cm線の観測量である輝度温度を見積もった。そして、Square Kilometre Array
であれば、100-1000時間の観測でWHIMとしてのミッシングバリオンを検出できるという結論に至った。これらの結果を報告する。
12月のセミナー
発表者
嵯峨 承平
日程/場所
12月8日(木)10:00-@ES606
題名
The cosmological
vector-mode, vorticity, and its observable
概要
宇宙論的摂動論のもとで摂動量はスカラー・ベクトル・テンソルモードに分解される。このうち線形ベクトルモードは必ず減衰するため、ほとんどの文脈では無視される。しかし、摂動を高次まで展開することでベクトルモードは可能となる。まず、前回の発表で結果まで出ていなかった、2次ベクトルモードが21cmレンズ効果に与える影響を報告する。
これまでの研究で、線形スカラーモードが作る2次ベクトルモードは現在に近いほど非線形性のため強く観測に影響を与えることが明らかにされた。
これに関連して、future workとして大規模構造におけるベクトルモードの役割を、渦度の保存則と関連付けて発表する。
また観測される銀河の相関関数にも、相対論的効果のひとつとしてベクトルモードが寄与する。その途中経過も可能であれば紹介する。
発表者
淺羽 信介
日程/場所
12月15日(木)10:00-@ES606
題名
Structure formation
with supersonic streaming motion in the Dark ages
概要
暗黒時代から宇宙再電離期にかけての構造形成を理解することは、現在の宇宙論のターゲットのひとつである。宇宙初期に形成される小スケールの天体においてはバリオンの運動が重要になってくる。Tseliakhovich
& Hirata
(2010)によって提唱されたバリオン-ダークマター間の超音速相対運動は摂動論から予言され必ず存在する効果であるが、その扱いに関してはまだ議論の余地がある。
我々は、球対称崩壊モデルを拡張することで、超音速相対運動がミニハローの形成に与える影響について研究を行った。本発表では、まず、球対称崩壊に相対速度を加えることで得られた結果を紹介する。そして、宇宙論的シミュレーションと比較することで、ハロー形成における不定性を含め超音速相対運動の影響について議論したい。
1月のセミナー
発表者
長谷川 賢二
日程/場所
1月12日(木)10:00-@ES606
題名
Development of a
radiative transfer core for simulating cosmic reionization
概要
Next generation telescopes and instruments designed to observe the intergalactic medium
(IGM) and galaxies during the epoch of reionization (EoR), such as SKA and Subaru-PFS,
will be in operation in a few years. Although the forthcoming observations will provide
us with fruitful information on the EoR, we need some theoretical models to understand
the reionization process by the observations.
For the purpose, we develop a radiative transfer code and directly simulate reionization
with the code. In my talk, I briefly explain important physical processes during the
EoR, and how we implement them into the code. Then I will show that the simulated
reionization history is well consistent with the current constraints by the GP trough
and the CMB polarization. I also present some preliminary results regarding the HI 21cm
and Lyman Alpha emitting galaxies during the EoR. Finally, I shortly introduce our
ongoing project ``MWA(SKA)-Subaru collaboration’’.
発表者
浦川 優子
日程/場所
1月19日(木)10:00-@ES606
題名
Inflation as a
probe of string theory and the observational imprints
概要
According to the up-to-date observations, the energy scale of inflation can be as high
as 10^{14}GeV. This fact indicates that inflation can provide us a natural accelerator
whose energy scale is by far much higher than the accessible energy scales by any
ground-based experiments. Given that there exist unknown particles which interact with
the inflaton, it may be possible to detect their imprints through various cosmological
observations. First, I'll discuss their imprints on large scale structures, following
Arkani-Hamed&Maldacena(15) and Schmidt et al. (15, 16). Second, I'll discuss
phenomenological imprints of axions, which appear rather generically in the 4D low
energy effective field theory of string theory.
2月のセミナー
発表者
竹内 太一
日程/場所
2月2日(木)9:00-@ES606
題名
High-z QSO number
count through redshifted 21cm line observation
概要
Observations of quasars at z>6 reveal the existence of supermassive black holes (SMBHs)
with a few billion solar masses in 1 Gyr after the Big Bang. Because of the difficulty
in observing quasars in higher redshifts, we have not yet got the details of their
formation process. However it can be expected that there exist a number of quasars as
the seeds of SMBHs before the epoch of reionization. In this talk, we focus on
redshifted 21 cm lines originated from neutral hydrogen hyperfine structure as a probe
of seed quasars in high redshifts. These signals depend on the physical conditions of
neutral hydrogen gas, e.g., density, temperature etc. Since quasars emit UV and X-ray
photons which can ionize and heat surrounding neutral hydrogen gases, quasars can
produce the specific spatial structures of 21 cm signals around them. Therefore, we can
probe the redshift evolution of quasar number count on redshifted 21 cm maps. Assuming a
simple model for the high redshift quasar distribution based on the Press-Shechter
formalism, we evaluate the feasibility of the quasar number count survey by the SKA
observation. We also discuss the potential of the SKA observation to probe the redshift
evolution of the quasar mass function which is deeply related to the formation of SMBH
in high redshifts.
発表者
角田 匠
日程/場所
2月2日(木)9:00-@ES606
題名
Dependence of escape
fraction on properties of galaxies
概要
Escape fraction is a key quantity to determine the contribution of galaxies to cosmic
reionization. Though many numerical simulations have predicted the LyC escape fraction,
the predicted values are different for each study. Since characteristics of the
simulations, e.g., resolution, implemented physics and numerical algorithm, are quite
different each other, it is usually difficult to understand what causes the diversity.
In this work, to understand what quantities of a galaxy are responsible for controlling
the escape fraction, we numerically evaluate the escape fraction by performing
ray-tracing calculations with simplified disk galaxy models. With a smooth disk model,
we first explore the dependence of the escape fraction on the disposition of ionizing
sources, and find that the escape fraction varies up to ? 3 orders of magnitude. It is
also found that the halo mass dependence of the disk scale height determines whether the
escape fraction increases or decreases with halo mass. With a clumpy disk model, it
turns out that clumps basically increase the escape fraction as far as the total clump
mass is less dominant, because LyC photons can effectively escape through gaps among the
clumps. We also find that the escape fraction is controlled by the covering factor of
clumps if the clumps are dense enough.
発表者
箕田 鉄兵
日程/場所
2月2日(木)9:00-@ES606
題名
Anisotropy of kSZ
effect generated by cosmological magnetic fields
概要
Magnetic fields in the universe are observed in various scales.In the primordial
universe, however, the structure of magnetic fields is known little, especially in
larger scales than Mpc because of observational difficulty. So we explored the model of
cosmological magnetic fields (CMFs) using anisotropy of kSZ effect. We assumed that the
primordial density fluctuations are generated by Lorentz force (Wasserman 1978). After
that, when the recombination is occurred and ionization rate is decreased, gases are
supposed to be heated through the process called “ambipolar diffusion” (Shu 1992).
Consequently, we could confirm the structure and intensity of CMFs with the power
spectra of y-parameter of kSZ effect. At this seminar, I will show the results of
calculating baryon density fluctuations generated by some CMFs’ models.
発表者
田中 俊行
日程/場所
2月8日(木)9:00-@ES606
概要
The first stars are the first luminous objects in our universe, which marked the end of
the dark age. Thus, there are still many theoretical models of first stars. Some
properties such as luminosity and spectral energy distribution can be investigated
through differential brightness temperature structure of 21-cm line coming from neutral
hydrogen surrounding a first star. The 21-cm line signal would be detected by
forthcoming radio interferometers such as Square Kilometre Array. In order to interpret
the observation, we need to investigate what each model of first stars look like in
21-cm line observation. In this work, we addressed the pressing issue with radiative
hydrodynamics simulation. That is to say, we took gas density profile into consideration
and investigated structures of differential brightness temperature. In addition, for
comparison, we conducted the simulation in the setup of Yajima & Li (2014) where gas is
treated as static and uniform intergalactic medium. Our result shows that first star is
somewhat easier to be detected than the prediction by the previous work owing to deeper
absorption line. Moreover, we will discuss differences of 21-cm signal in different
evolution times.
発表者
飯田 遼
日程/場所
2月8日(木)9:00-@ES606
題名
Axion inflation with
interference and CMB anomaly
概要
Observations of cosmic microwave background(CMB) by WMAP and Planck indicate that there
are about 3sigma deviation between observational data sets and theoretical prediction
from simple inflation models at large scale .This is called CMB anomaly.
In this work, we search the model of axion inflation which is derived from super string
theory.From the model, we obtained the primordial power spectrum has interference,in the
model the potential has differ frequency oscillation terms. And we set a limit to the
model's parameters region. Then we will study how much to improve chi-square compere to
LambdaCDM model.
In this talk, I’ll talk about feature of primordial power spectrum and progress of my
work to limit parameters region.
発表者
簑口 睦美
日程/場所
2月8日(木)9:00-@ES606
題名
Redshift
evolution of the ellipticity of cosmic voids
概要
As the redshift survey progresses and the amount of data released, cosmic voids, the
regions surrounded by clusters of galaxies, are attracting more and more attentions of
researchers. Some of them trying to estimate cosmological parameters from the
observational data, comparing N-body simulation data (e.g. N. Hamaus et al. (2015), S.
Nadathur (2016)). On the other hand, there are works about analytical approaches on the
large scale structure of the universe, which try to describe evolution of density
fluctuation by means of perturbation theory or by “exact” solution for simplified models
(e.g. M. Bruni et al. (2014), R. A. Sussman et al. (2017)). While many interesting
problems about void structures are remain to be solved, the main purpose here is to
answer the question that whether the relativistic effects on void structures are
observable. For this purpose, first I applied latter works mentioned above to isolated,
axial symmetrical void structures and examined how their shapes grow in each of
Newtonian and Relativistic methods. And then I compared the results with those in
observation (SDSS DR11) and simulation (500Mpc^3, Np = 128) data. In this talk, I will
show results provided so far.
発表者
小林 将人
日程/場所
2月16日(木)10:00-@ES606
題名
Evolutionary
Description of Giant Molecular Cloud Mass Functions across Galactic Disks
概要
Recent radio observations show that giant molecular cloud (GMC) mass functions
noticeably vary across galactic disks (e.g., Colombo et al. 2014). High-resolution
magnetohydrodynamics simulations show that multiple episodes of compression are required
for creating a molecular cloud in the magnetized interstellar medium (e.g., Inoue et al.
2012). To understand the time evolution of GMC mass functions, we formulate the
evolution equation for the GMC mass function to reproduce the observed profiles, for
which multiple compressions are driven by a network of expanding shells due to H II
regions and supernova remnants. We also introduce the cloud-cloud collision (CCC) terms
in the evolution equation in contrast to previous work. In this seminar, I would like to
present computed time evolutions and the following two suggestions: (1) the GMC mass
function slope is governed by the ratio of GMC formation timescale to its dispersal
timescale whereas the CCC effect is limited only in the massive end, (2) almost all of
the dispersed gas contributes to the mass growth of pre-existing GMCs in arm regions
whereas less than 60 percent contributes in inter-arm regions. Our results suggest that
measurement of the GMC mass function slope provides a powerful method to constrain those
GMC timescales and the gas resurrecting factor in various environments across galactic
disks.
発表者
Jean-Baptiste Durrive
日程/場所
2月17日(金)13:00-@ES606
題名
Fragmentation of
baryons in the Cosmic Web
概要
Cosmological numerical simulations suggest that the Universe has a web-like structure,
the nodes of which are galaxy clusters. These clusters are supplied with matter by gas
flowing along the filaments interconnecting them. Part of this accretion occurs
intermittently, which indicates that dense clumps of matter do not only form inside
clusters themselves, but also either in voids, walls and/or filaments. I investigate the
possibility that these clumps formed inside filaments and walls, through gravitational
instability. The aim is to derive both general instability criteria and dispersion
relations, to predict under which conditions and in which areas inside the structure
such clumps may form, and to compute their typical size and growth rate. To do so, I use
methods developed by tokamak physicists, that I adapt to the cosmological context.
発表者
西澤篤志
日程/場所
2月17日(金)13:00-@ES606
題名
Gravitational-wave
propagation as a probe for cosmology and test of gravity
概要
The direct detections of gravitational waves (GW) from merging binary black holes by
aLIGO have opened a new window to astronomy, cosmology, and testing gravity. In this
presentation, I will show that GW propagation can be a powerful probe for cosmology and
test of gravity, limiting topics to what can be done with aLIGO in a couple of years. In
the first part, I will talk about a measurement of the cosmic expansion rate with BBH
and show that it is sensitive enough to resolve the discrepancy problem of Hubble
constant measured by other astrophysical means. In the second part, I will focus on a
future GW observation of neutron-star binaries and discuss the direct measurement of GW
propagation speed and implications to modified gravity theories. Finally, I will present
a general framework for testing gravity with GW propagation.
発表者
堀口晃一郎
日程/場所
2月23日(木)10:00-@ES606
題名
Oscillations in
the CMB angular power spectra at ell-120
概要
Cosmic Microwave Background (CMB) has been well known as a proof of the hot big bang
model. In recent years, thanks to the precise observations by WMAP and PLANCK
satellites, we come to see the detailed structure of CMB temperature (or polarization)
fluctuations. In this work, we forces on the irregular oscillations of their angular
power spectra around multipole ell~120. These oscillations were indicated in the
analysis of WMAP5 data by Ichiki et al. (2010). We look for these oscillations in the
2015 year's PLANCK temperature and polarization data by adopting a Markov-Chain
Monte-Carlo (MCMC) method. We find the oscillations in the data at ell ~ 123.5 and their
amplitude is about 3.7*10^{-9}, which are consistent with those found in the WMAP5 data.
In this presentation, we talk about the result of the MCMC analysis and the influence of
the oscillations to the other cosmological parameters.